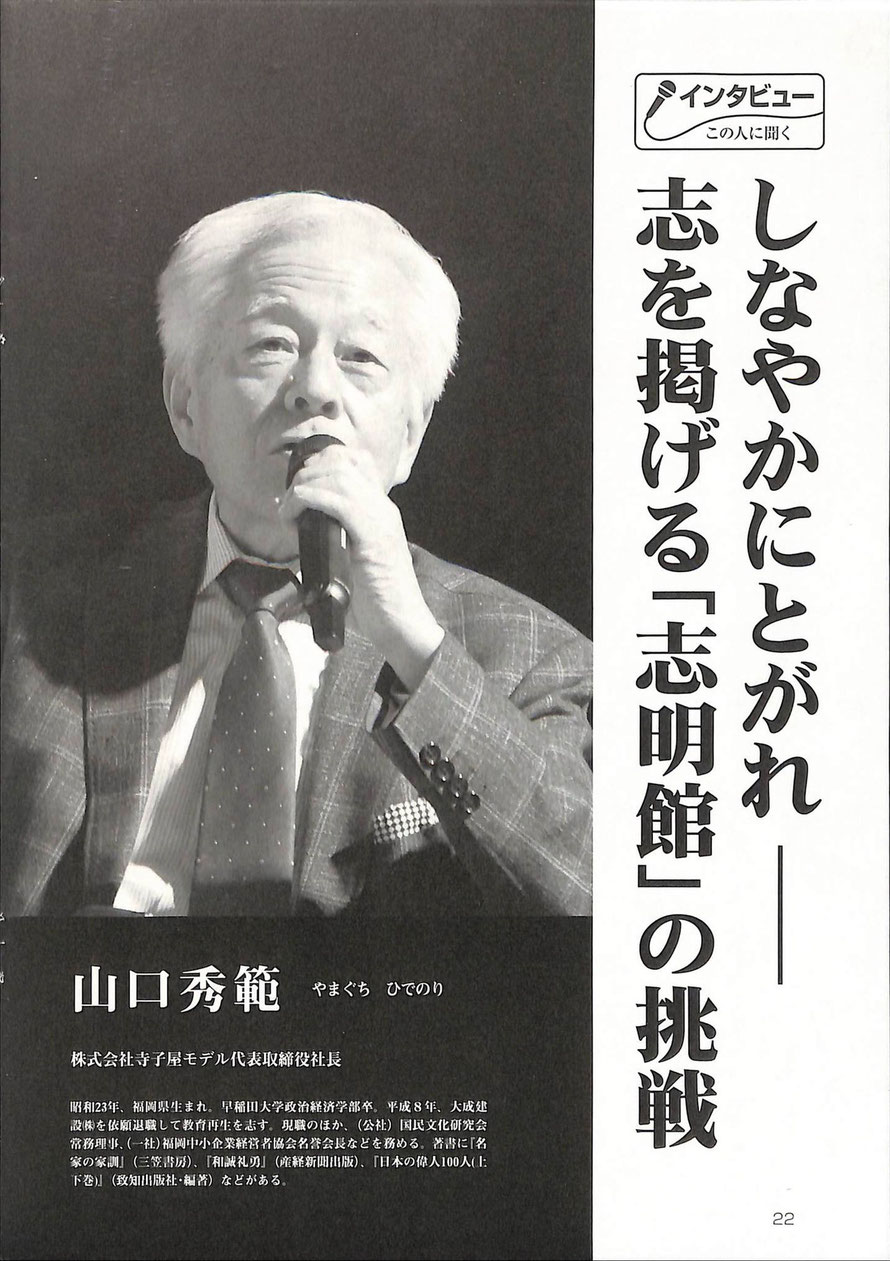
習得活用の「土台教育」・偉人伝を使った「人間力教育」・自分で課題をみつける「発憤教育」。これが『志明館」の三本柱です。
今日本で私立の小中学校新設と言えば、得てして英語教育や国際化教育といったことがクローズアップされがちだが、誇りと志をもったリーダーを育てることをめざした小中一貫校が来年四月に北九州市に開校することになり、注目を集めている。この学校設立の推進者の一人である株式会社「寺子屋モデル」社長の山口秀範さんに話を聞いた。
― 誇りと志をもつ入材を ―
― まずは、来春北九州市に設立される小中一貫校の建学の理念といった辺りからお聞かせ下さい。
山口 わが「志明館」は教育理念として「誇りと志を培い、日本で世界で羽ばたく人財を輩出する」を掲げています. つまり、志を正面に掲げて、世界で活躍する人材を育むということです。
この理念を今の親御さんにも分かっていただけるよう、保護者向けのバンフレツトの表紙に、「しなやかにとがれ」というキャッチフレーズで表現しています。どういうことかと言うと、われわれが受けてきた教育は横並びなんですね。先生が教室で一方的に教壇から知識を子供たちに与えて、子供たちはそれを真面目にノートに取っていく 日本では明治以降ずっとそういう教育がなされてきたわけです。
けれども、日本が世界に伍していくためには、これから日本のリーダーとなる人材一人ひとりが、自分が持っている能力をしつかり自覚して、それを磨くという意味で「とがる」ことが必要だと思うのです。
ただし、「とがれ」と言っても、自分勝手にとがるのでは困る。やはり、相手のことを思いながらとがらしていくという意味で、「しなやかに」という言葉を加えているのです。
もちろん、そうした一人ひとりの人格や能力を磨くこととともに、同時に誰かのため、何かのために、できれば自分よりももっと大きなもののために、自分のできる最大限を尽くす。そういう気持ちを小学生の時から併せて持たせようというのが「志の教育」だと思っています 確かに、みんな自分が一番かわいいわけですけれども、やはり自分のためだけに生きるというのでは志にはならない。
志を持つとは、言い換えれば「使命感」を持つという意味でもあり、自然と「志明館」という校名になったということです。
― 土台教育・人間力教育・発憤教育 ―
― そうした「しなやかにとがれ」との理念は、具体的にはどのように学習内容に反映されるのでしようか。
山口 今の公立の小中学校の授業は約約一千時間ありますが、その約七割五分は、先生が国語や算数といった基礎的な知識を与える「習得活用」と呼はれる時間です。要するに、知識や技能を身に付けさせる時間なのです。
では、残る二割五分で何をやるかというと、道徳に一割から割五分、加えていわゆる発展探究学習に一割程度。発展探究学習は探究という習得活用を少し発展させて、自分で何かを考えようという時間です。
こうした枠組みは、学習指導要領で定められており、守らなければならないわけですが、でもそれ以上やることについては問題視されないことになっている。そこで、志明館では全部で一年間千三百時間、公立より三割ほど多い時間を始めから確保しています。というのも、一年生から夕方までずっと学校にいてもらうとともに、土曜日も隔週で授業をします。それやこれやを加えると、三割方時間が多くなります。
一方、学習全体の割り振りはどうかというと、「土台教育」「人間力教育」「発憤教育」の3本柱とし、まず土台教育は、先ほど触れた国語や算数などの習得活用の時間に当たるものです。公立がこれに全体の七制ほど割いているのに対して、その方法は後でお話しますが、私たちは千三百時間のうちの半分又は半分以下で済ませられると考えています。
次の人間力教育は道徳に該当するものですが、習得活用の時間を縮めた分、公立の倍以上時間を割けることになります。残りの発展探究学習に当たるのが「発憤教育」です。これは、論語llの中で孔子が弟子に向かって、自分たちで何かを発見しようとか、何かを表現しようという必死の思いが溢れていなければ、先生は二度と教えないという箇所の、「憤せざれば啓せず、悱せざれば発せず」から名づけました。
― 習得活用の時間を短くして、人間力教育と発憤教育に時間をかけるということですね。
山口 その通りですが、どうして習得活用の時間を短くできるかと言うと、そこには二つの理由があります。一つは、現在の九年間のカリキュラムを経験豊かな先生方にも手伝ってもらってすべて見直したのです。そうしたらどの教科にも意外と重複や反復が多かった。それを整理するだけで、公立が九年間でやることを、八年か七年半ぐらいでできそうなのです。
二つ目は、AI搭載アプリといういわば新兵器の活用です。例えば、計算問題や漢字の書き取りをアプリが進めます。子供たちがチャレンジしてできなかったらだんだん易しくなったり、ヒントを出したりする。正解できるようになると、アプリの判断で次第にレベルが上がっていく。これは、先生がいなくても自分でできます。記憶力に特化した「モノグサ」というアプリを開発した若い起業家と連携します。
こうした工夫によって習得活用(土台教育)の時間が大幅に短縮できると同時に、子供たちの理解力や定着力は、格段に上がります。
― 「人間力」は偉人伝から ―
― 三本柱のうち、人間力教育は具体的にはどのようなものになるのでしょうか。
山口 人間力の基礎は何と言っても日本の偉人の生き様を伝える偉人伝教育です。授業では週二回は偉人伝に触れさせる予定で、そのために「寺子屋三部作」というバイロット版の教科書を作製しています。偉人伝、素読暗唱、伝統文化・礼儀作法の三冊です。子供たちが志明館に在学する九年間のうち、実質七年間は使用しつづけるいわば基本図書にしたいと考えています。
偉人伝で取り上げたいのは大体長年やってきた「寺子屋」で取り上げてきた人物です。出光佐三、ヘレン・ケラー、牧野富太郎、宮沢賢治、野口英世、ナイチンゲール、福澤諭吉、二宮金次郎、中江藤樹、須佐之男命などが一期で、これをまず二年間でやる予定です。
― 発憤教育についてはどうですか。
山口 発憤教育では、例えば自分が何かに興味を持つとか、得意なことを見つけ出すなど、教科書には書いていないことをやらせます。要は、自分で課題を見つけて、解決まで行きなさいということです。
ただ、小学一年生で自分で課題設定というは難しいので、初めはある程度誘導型で行くつもりです。「君は何が.番面白いと思うのかな」と先生が少し誘導するわけです。
一方、時間割の大きな括りで言えば、土台教育と人間力の教育は午前中に机について教室で授業をする。午後は発憤教育の時間を基本としてあえて教室にいなくていい時間にしたい。小学一・二年生の頃は泥んこになって夕方まで遊ばせたい。そうしたなかから、何か発見すればいいと考えています。
例えば、ロボットに興味がある子供がいれば、町工場の社長さんを紹介してあげるから、自分でいろいろ聞いておいでと。この点、北九州はもの作りの伝統が生きているから適しています。一例に過ぎませんが、子供たちが各々の興味や関心があること、まさに「とがっていける」題材に出会うことが発憤の契機になるということです。
― 偉人伝教育、発憤教育、何とも画期的ですね。
山口 来年の開校を前に、児童募集の一環として一種の体験教室を時々やっていて、保護者のの皆様にも、土台と人間力と発憤の各教育が志明館の特徴であるとアピールしています。いずれの教育にも関心を持ってくれますが、特に偉人伝やレゴ(プロツク玩具)を使ったコミュニケーション授業は評価が高いようです。
― 日本の子供たちの表情が冴えない —
― ところで、山口さんがこうした学校の設立を思い立たれるに至ったきっかけは何だったのですか。
山口 私は元々大手ゼネコンに二十五年ほど勤めており、そのうち十五年間は海外で勤務していました 西アフリカのナイジェリアに三年半、ロンドンに二年、アメリカにも八年半ほどいました。
今から三十年前に海外勤務を終えて久々に日本の本社勤務となったのですが、通勤で自宅から駅までの十分間ほどの間、登校中の小学生たちと毎朝すれ違ったのです。すると、日本の子供たちは本当につまらなさそうな顔をして歩いていた(笑い)。 笑顔もなければ会話もない。ただ黙々と歩いていた。私にとって本当に大きなショックでした。
というのも、ナイジェリアの子供たちは元気でもっと生き生きとしていましたし、出張したことのある中南米のドミニカ共和国などは本当に貧しくて悲惨な国ですが、子供たちはやはりキラキラと輝いていた。日本の子供たちの表情が極瑞に冴えないというショックがすべての始まりでした。
そんな思いを抱えなから、結局東京の本社に二年ほどいたのですが、その間、われわれ団塊の性代が子供の頃はみんな貧しかったけど結構元気があったのにどうして飽食の時代の子供は元気がないのか。そこで諦めてしまえば二、三十年後の日本をこの子供たちがちゃんと支えてくれるのか。そんなことをあちこちで言い、何とかしなければと考えていたとき、フッと自分が若い頃に力を与えてくれた偉人伝が思い出されたのです。
それで、偉人伝を子供たちに届けるために会社を辞めて補岡に帰り、試行錯誤の末、平成十七年に「寺子屋モデル」という会社を創立しました。しかし、昨日までゼネコンにいた男が子供たちを集めて偉人伝を語ると言つても、初めは誰も見向きもしない。そんな日々がしばらく続きましたが、次第に少しずつ注目されるようになっていったのです。
― 師との出会い 同志との出会い —
山口 実は、私が偉人伝に惹かれるようになった原点は、修猷館高校時代に国語の先生だった小柳陽太郎先生と出会ったことにあります。
当時、毎週全曜日だったと思いますが、先生のお宅でいわば小柳塾が開かれていたのです。 クラブ活動が終わった夕方、先生のお宅に同期の一癖ありそうな連中が集まってくる(笑い)。当時はまだガリ版刷りの時代でしたが、先生は今日は吉田松陰、次は山鹿素行といった具合にブリントを用意して下さり、私は三年生の四月の終わり頃からその年いっばいまで七、八カ月間参加し続けました。それが私にとって、いわば学問の入口の原点みたいなものになったという思いはずっとありました。
一方、学校の設立に踏み出す上で決定的だったのは、学校法人博多学国理事長の八尋太郎氏という同志との出会いでした。博多学園は、福岡市内に高校と医療系専門学校を有する他、幼椎園を七つも経常する少し変わった学校法人なのですが、実は志明館も博多学園が経営母体です。
八尋氏は、今から十七年前に父親の後を継ぐために、鉄鋼会社を辞めて突然教育界に身を投じたという異色の経歴の持ち主です。彼は福岡に戻って、まず高校の校長をやれと父親に言われて、随分苦労をされたのですが、そうした時に、ある方が「あなたのように教育界じゃないところから教育をやっている人がいる」と言って、私を紹介してくれたのです。
それでいろいろ話をしているうちに、世の中の常識が学校の中では通じない(笑い)と、まさに意気投合したのです,それなら世の中の常識が通じるような学校を作ればいい、ます小学校から作ろうとなったのです。これが、志明館設立への具体的な出発となりました。
私自身は会社を辞めて、寺子屋を始めて二十数年になりますが、その間も、やはり本丸は小学校だという思いはありました。小柳先生がご健在の頃に、先生のお宅でご馳走になっている夜更けに「山口が昔言つていた学校はまだできないな」と先生がボソッと言われました。私は学生の時にそんなことを口走ったらしいのです。先生は新しい学校を誰かが作ってくれるだろうと思っておられたのかもしれません。
そんなこともありましたので、八尋氏と出会った時から、よしそれでは本当に学校を作ろうと決意し、一気にここまで来たというのか率直な感想です。
―「応援団」は福岡経済界 —
― とはいえ、学校を一から作るとなると、いろいろな面で「応援団」が必要かと思います。
山口 私たちが本格的に学校を作ろうと言い出した十五年前、まず日本一の学校を作るための勉強会みたい なものを立ち上げました。
私の同級生でもあり、福岡経済界の中心だった石村善悟氏―石村萬盛堂というお菓子屋の社長― を筆頭に当時はまだ数人でしたが、それが最初の母体でした。その後、リーマンショックをはさんで、本格的に福岡の経済人を中心に発起人会を作ってもらったのが十年前。九州電力やJR九州といった地元経済界の中心的な方々に大勢加わっていただきました。
地場の経営者の中にも世を憂えたり、郷里のことに関心を持っておられる方は結構いらっしゃり、現在は開校賛助会と名前が変わりましたが、三百五十人ほどが応援団となってくれています。
― やはり、今の教育がこれでいいのかと憂えている方は多いということですね。その意味では志教育を前面に掲げた学校ができるということは、大いに価値あることだと思います。
山口 もちろん志というのがこの学校の一番の中心理念なのですが、色々の工夫が必要です。
保護者も現代の日本人ですから、先ほど説明したAlアプリのこととか、「発憤」という聞き慣れない言葉だけれども、あなたのお子さんが持っている一番良いものを引き出すんですよ、ということと合わせながら呼びかけもいるのです。
若いお父さんやお母さんの中にも、やはり今のままでは日本の将来に不安を覚えるという気持ちを持っている人がだんだん増えてきている、という感触はあります。
― 最後に、今後のスケジュールについて少しお聞かせ下さい。
山口 来年の開校時、一年生を―クラス三十五人で2クラス分、七十人募集します。二年生は地元の公立の一年生が二年生になる時に転校して志明館に入学してもらう予定で、これは―クラス分集まればいい。その3クラス分を来年四月に開校させる予定です。
ちなみに、中学校の開校は令和十一年四月の予定ですから、中学校を卒業する生徒が誕生するまでには十年近くかかるということです。
― もう募集は始まっているのですか。
山ロ 十月中旬から願書の受付ですから、現時点ではまだまだ全く予断は許しません。
志明館で育った子供たちが本当に日本の中核になっていくには二十年三十年かかるわけですが、対症療法で何とか日本を持たせていくということをやりながらも、本当に本来の日本人の力を取り戻すためには初等教育からやらなけれはならないという思いは皆さんお持ちです。ですから、第一号として具体化する志明館を是非とも形にしたいと強く思っています。
― 志明館の開校に心より期待し、発展をお祈りしています。
(令和5年8月7日取材 文責・編集部)
■小中一貫校「志明館」については、以下にお問い合わせ下さい。
学校法人博多学園 志明館開校準備室
〒803-0837
北九州市小倉北区中井口4番1号
TEL:093-383-0514
FAX:093-383-0504
ご連絡等ございましたら、連絡フォームを使ってお送りください。
なお、歴史講座は先着順ですので、予約等は承っておりません。